
-
お電話でのお問い合わせ090-6367-7604
- メールフォーム
お電話でのお問い合わせ090-6367-7604

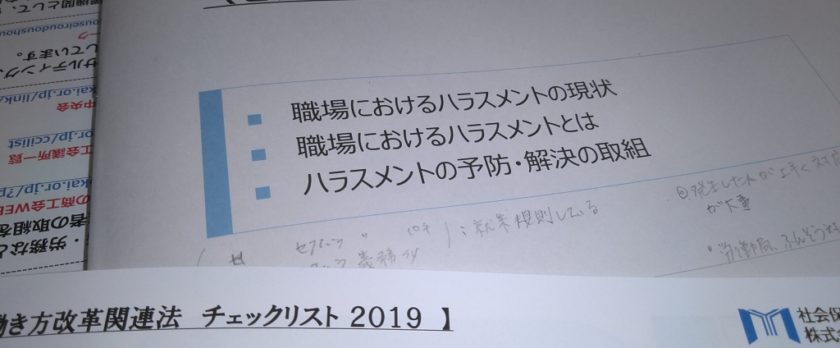
愛知の開業保健師 健康経営エキスパートアドバイザー 水越真代です。
職場のハラスメント対策セミナーを受講してきました。
ハラスメントというとパワハラ、セクハラ、マタハラなどが有名ですが、メットで調べると軽く30くらいは出てきます。
定義を調べてみると以下のように出てきました。
ハラスメント(Harassment)とはいろいろな場面での『嫌がらせ、いじめ』を言います。その種類は様々ですが、他者に対する発言・行動等が本人の意図には関係なく、相手を不快にさせたり、尊厳を傷つけたり、不利益を与えたり、脅威を与えることを指します。
ここで大事なのは、
◆行為者の意図に関係ないこと、
◆相手に不利益を与えること
ということです。
セクハラは1999年施行の改正男女雇用機会均等法で事業主の配慮義務を定め、2007年から事業主に防止措置を義務付けていいます。
マタニティーハラスメントは17年から同法と改正育児・介護休業法で事業主の防止措置を義務化。
パワハラは今国会で労働施策総合推進法を改正し初めて防止措置義務を規定し、年内には詳しい通達が出るとのこと。
事業主の実効性のある対策が求められています。
事業主の対策としては、予防策、そして起こったときの適切な対処の2つの柱。
対策のポイントは、何がハラスメントなのかの明確化、相談窓口の設置、プライバシーの保護、厳正な処分を明確にすること
それを社員にきちんと周知することが予防策として大事とのことです。
本当にそうですよね。
会社が何をしようとしているのか、どのように規則をかえたのかを社員にきちんと知らせること
そうしないとせっかくやった対策が浸透しませんものね~
もうこれは繰り返し、いろいろな手段でする これにつきます。
詳しくはこちらを
さてこの研修を受けて、個人的な一つの違和感。
行為者は処罰されて終わり??
水戸黄門ではないのだから・・行為者は処罰されて一件落着みたいなことは現実あり得ないと思うのです。
もちろん、された人の保護が一番です。
そのうえで、行為者もそうせざる負えない背景を抱えた人として見る必要があるのではないでしょうか。
行為者がそうせざる負えなかった背景にきちんと向き合い、どのように行動をとったらよかったのか、
行為を繰り返さないためにどうしたらよいのか、をサポートするプログラムが必要なのではないか。
それを事業主が行うことで、今後の会社の生産性を高めることにつながるのではと思います。
具体的には、半年ぐらいのプログラムで、個人セッションかな・・・
もう少し具体的に考えてみようと思います。
この記事へのコメントはありません。